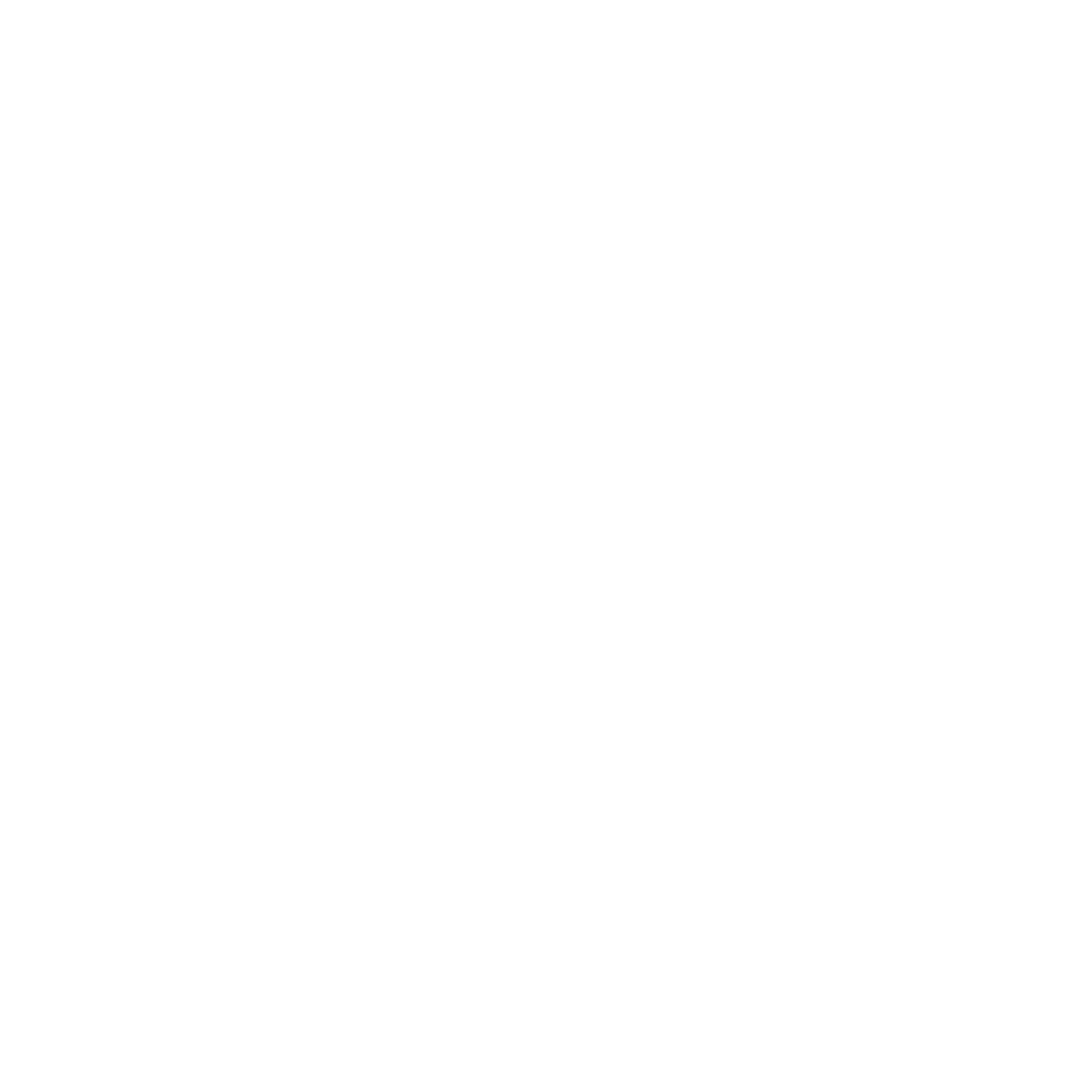九月下旬の夜明け前。
カナリアは死んでいた。
いつの間にか時計の針も止まっている。
窓際、カーテンの下にいるナツキからは呼吸の音が聞こえてこない。
あの神経質なほど綺麗好きだったナツキが、自分の排泄物の上に横たわったまま動かない。
ここからだと、生きているか死んでいるかもわからない。
キョウコは床に転がっていたビンを掴み、ナツキの頭に投げてぶつけてみる。
ビンが当たった瞬間、微かにナツキの指先が動いた。
……どうやら、まだ生きてはいるようだ。
床には脱ぎ捨てた衣服とゴミの入ったビニール袋が錯乱し、部屋中に異様な湿気と悪臭が充満している。
キョウコは足元に注意してリビングへと向かう。
リビングの壁には鏡が立てかけられており、暗い部屋にたたずむキョウコの全身をぼんやりと映し出していた。
服は着ていなかった。
いつからなのか、わからない。
そんなこともう気にかける必要はなかったから。
あばら骨の浮き出た醜い身体も、これで見納めとなるだろう。
ガスコンロの横に備え付けている冷蔵庫の扉を開くと、庫内の光に照らされて、暗い部屋にしゃがみ込むキョウコの影が伸びていた。
汗ばんだキョウコの身体を、冷蔵庫の冷気が心地よく冷やす。
隅々まで見渡しても、もう冷蔵庫には何も入っていなかった。
飲み物も、食料も、何も。
リビングの棚に目を向けてみるが、やはり何もおいていなかった。
もともと料理をする者はいなかったので調味料の類もない。
唯一、二人掛けのテーブルの上に、親指サイズの塩の瓶と、黒砂糖の袋が置いてあるだけだった。
キョウコは、流し台においてあるコップを掴み、中の濁った液体を捨て、洗うこともなくそのまま水道の水を注ぎ入れて飲み干した。
そしてコップを流し台においたあと、タンスの引き出しを確認する。
茶色い封筒には、紙幣は一枚も入っていなかった。
もう、何も買うことはできない。
いよいよ最後の日がすぐそばまでやって来たようだ。